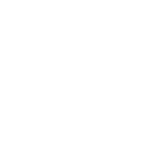主体感:「自分が行っている」という感覚

何かしらの行為をしたときに、自分がその行為の主体であると言う実感を主体感(the sense of agency)と呼びます。正しく理解するための例として、こんな日常場面を考えてみましょう。
大学から自宅に帰り、自分の部屋に入ります(途中で、家族とおしゃべりをしたり、飼い猫や飼い犬と遊ぶかもしれません)。窓の外がもう暗かったので、カーテンを閉めて、壁のスイッチを押しました。部屋の電気がつきました。
この時、おそらくは、「自分が電気をつけた」ことを疑うひとは誰もいないでしょう。なんと言っても、スイッチを押したのは自分自身です。でも、よくよく考えてみると、これは実に不思議なことです。スイッチを押すと言う行為と、電気がつくという現象は、はたから見れば、独立しています(もちろん、中身の仕組みとしてはつながっているでしょうが、信号が到達するところを目で確認しているわけではありません)。もし仮に、自分が押したスイッチがこっそり誰かの仕掛けたハリボテだったとしても、同じタイミングで電気が付いたのであれば、その差を言い当てることはできません。私たちは、自分の行為のあとに起こった現象を、自分の行為による結果と思い込んでいるだけなのです。
そうなると、自分の行為の実感が何やら怪しげなものの上に成り立っているような気がしてきますが、この思い込みは、生物が生きていくうえで非常に重要です。自分が置かれた環境において、自身の行為が何に対しても作用しないと思っていたなら、動くことはできません。それがいかに生存競争に不向きかは明白でしょう。
さて、それでは、主体感のメカニズムとはどんなものなのでしょう?コンパレータモデル(Blakemore, Wolpert, & Frith, 2000)と呼ばれるモデルでは、行為の結果が、実際に行為が行われる前に予測され、その予測した結果と実際の結果が比較されることを想定しており、この2つの差分が大きくなると、主体感を感じにくくなると説明しています。つまり、先ほど挙げた例で言うならば、電気をつけようと意図した時点で、私たちの脳は「電気がつく」という結果を予測しています。そして、実際に起こった現象が、予測と同じ、「電気がつく」だったので、主体感を感じたということになるのです。
近年、自動運転車をはじめとする自動化技術が目覚ましい発展を遂げており、私たちの生活と切り離せないものになっています。生活が便利になる一方で、こうした自動化技術をめぐる議論の中では、使用者に主体感を失わせないようにするにはどうしたら良いのか?という問題がしばしば取り上げられます。主体感は、いま注目の研究トピックかもしれません。