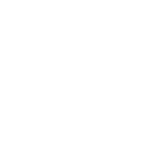セルフ・サービング・バイアス:いいことは自分のせい?

生まれて初めて取り組んだスポーツなりゲームなりで思わぬ成功納めてしまい、ご都合主義にも「自分には才能がある!」と思ってしまう、そんな経験をした方もいらっしゃるのではないでしょうか。私は小学校低学年の頃に初めて行ったボウリングのファーストショットでストライクを決め、その瞬間プロボーラーになるという宣言をしたのですが、その数時間後には撤回した部類です(父曰く、ボウリングのビギナーズラックはわりとあるとのこと)。
こうした自分自身の結果を都合よく解釈しがちな傾向は、セルフ・サービング・バイアス(self-serving bias)と呼ばれており、自分の成功を内部的な要因(能力や努力)に、失敗を外部的な要因(運や他人の行動)に帰属することを指します。
さて、前回のコラムで主体感(the sense of agency)のお話をしましたが、覚えておられるでしょうか?主体感とは、自分でスイッチを押したタイミングで電気が点いた場合に「電気を点けたのは自分だ」と思うような、何かしらの行為をしたときに、自分がその行為の主体であるという実感のことでした。
それでは、こんな場合を考えてみましょう。自分の行動に、自動システムがこっそり介入して結果を操作してくるような状況です。ボウリングで自分の投げたボールの軌道がこっそり補正されるようなシーンを考えてもらうとわかりやすいかもしれません。こんな時、私たちの結果(ボールの軌道やボールが倒したピンの数)に対する主体感はどのように変化するのでしょうか?
ある実験では、システムが介入する方向として実験参加者にとって良いもの(嬉しい結果になる)と悪いもの(嬉しくない結果になる)の2つの方向を設定し、また介入の度合い(%)を変えて、実験参加者の結果に対する主体感がどのように変化するのか検討しています(Ueda et al., 2021)。その結果、同じ介入度合いにも関わらず、実験参加者にとって嬉しい結果になる場合は自分の結果への主体感が増し、嬉しくない結果になる場合は下がることがわかりました。まさにセルフ・サービング・バイアス!という感じですね。
ChatGPTをはじめとして、現代ではAIを搭載した便利なツールや自動化技術が多く開発されており、日常生活におけるテクノロジーとの関わり方は複雑さを増しています。もちろんそうした技術的進歩の恩恵は受けるべき(そうでないと時代に乗り遅れてしまうので)だと思いますが、その結果を自分たちが都合よく帰属する可能性があることも、たまには意識しておく必要があるかもしれません。
Miller, D. T & Ross, M. (1975). Self-serving biases in the attribution of causality: Fact or fiction?. Psychological Bulletin, 82(2) 213-225.
Ueda, S., Nakashima, R., & Kumada, T. (2021). Influence of levels of automation on the sense of agency during continuous action. Scientific reports, 11(1), 2436.