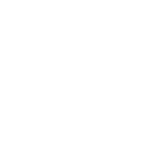比較発達心理学の授業風景:自己認識について

「比較発達心理学」では、人間以外の動物や乳幼児との比較を通じて、「こころ」の進化や発達について考えます。この日のテーマは「自己認識」でした。
鏡像自己認識とマークテスト
自己認識の能力を評価する方法の一つに、「マークテスト(ミラーテスト)」があります(Gallup, 1970)。このテストでは、身体の見えにくい部位にマークを付け、鏡を見せた際にそのマークに触れるかどうかを観察します。チンパンジーはこのテストに合格することが知られており、鏡に映った自分の姿を見て、顔や身体の見えない部分を調べる行動を示します(図1)。さらに、自分の後ろ姿をライブ映像でモニター越しに見た場合にも、自分の顔や身体の特定部位を観察する行動が報告されています(Hirata, 2007)。

行為の主体感(Sense of Agency)
私たちは、「自分がその行為を行っている」という感覚にも非常に敏感です。例えば、複数人でテレビゲームをしている際、自分が操作しているキャラクターをすぐに識別できます。このような感覚は「行為の主体感(sense of agency)」と呼ばれ、自分の意図した行動とその結果を結びつける認知的なプロセスを指します(上田先生のコラムも参照)。
チンパンジーも同様に、「自分がその行為を行っている」という感覚を持つのでしょうか?Kaneko and Tomonaga(2011)の研究では、チンパンジーにトラックボールを操作して画面上のカーソルを動かす訓練を行い、その後、2つのカーソルのうち自分が操作しているものを識別できるかを調べました。その結果、チンパンジーは自分が操作しているカーソルを高い正答率で選択することができました。さらに、カーソルの動きに時間的な遅延や空間的な歪みを加えると、正答率が有意に低下することが示されました。これらの結果は、チンパンジーが行為の主体感を持っている可能性を示唆しています。
自己認識が揺さぶられる体験
最後に、私自身が体験したメディア・アーティスト藤幡正樹さんのインスタレーション作品『無分別な鏡』(2005)を紹介したいと思います。これは、鏡のような仮想現実空間をVRで再現した作品です。専用のメガネをかけて「鏡」をのぞくと、部屋の様子はちゃんと映っているのに、自分の姿だけが消えていて、かけているメガネだけが宙に浮かぶように見えます。身体を左に動かせば、メガネも一緒に左へ動きますが、やはり姿は透明なまま。この非日常的な体験が、不思議な感覚を呼び起こし、自分という存在のあり方が揺さぶられるように感じられます。
この授業を通じて、自己認識の多様な側面とその評価方法について学ぶことができます。動物や乳幼児の研究から得られる知見は、人間の「こころ」の理解にとっても非常に重要です。
- 藤幡正樹(2005). 無分別な鏡. NTTインターコミュニケーション・センター(ICC)https://www.ntticc.or.jp/ja/feature/os10/2006/#unreflective-mirror
- Gallup Jr, G. G. (1970). Chimpanzees: self-recognition. Science, 167(3914), 86-87.
- Hirata, S. (2007). A note on the responses of chimpanzees (Pan troglodytes) to live self-images on television monitors. Behavioural Processes, 75(1), 85-90.
- Kaneko, T., & Tomonaga, M. (2011). The perception of self-agency in chimpanzees (Pan troglodytes). Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences, 278(1725), 3694-3702.