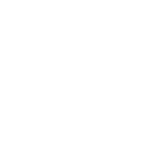脳を測る

心理学において脳科学的な手法をとることは、その手法に対する賛成や反対も含めて、伝統的に様々な手法が検討されてきた。代表的なものが電気的な信号であるEEG(脳波)であるが、近年、授業や実習、また卒業論文などの手法としてもよく用いられるようになってきているのが、近赤外分光法(NIRS: Near-infrared spectroscopy)である。筆者のゼミ生の卒業論文の手法としても、近年NIRSを用いたものが増加している。NIRSは頭部の洗浄なども必要なく、また最近では比較的安価な装置も販売されており、各大学のHPでもNIRSを使った研究が「脳科学」として宣伝されているのを目にすることがある。
NIRSは、MRIやMEGなどの大規模な装置に比べると、頭部の動きに対してもそれほど制約がなく、乳児や発達障害児の脳計測などではしばしば用いられてきた。筆者も、NIRSを用いて乳児の脳活動の計測の多くの論文に関わってきたが、発達障害児を対象に大学病院と協力しながら脳活動の検討も実施してきた。病院での実験では、ゼミ生、大学院生の手も借り、現在も定期的な研究活動を行っている。
NIRSは、ミリ秒単位の短時間で反応するニューロン活動を、電気的に捉えるわけではなく、数秒オーダーで発生する血流反応を捉えて、間接的にニューロン活動を推定する方法である。この時間の「長さ」を前提にすると、ある意味で実験心理学における時間制御に厳密な計画の必要がない。例えば臨床的な検査場面での脳活動も、NIRSを用いれば計測可能であり、自由な会話や投影法の検査などの際にも使えるので、たいへん便利な道具であるともいえる。こうした応用的な研究はいずれも論文にもなっており、ご興味ある方は、筆者と中央大学の檀一平太先生とで共同編集した、Japanese Psychological ResearchのNIRS特集号を参照いただきたい(Kanazawa & Dan, 2018)。
さて、ここまでNIRSの強みを強調してきたが、現代の脳科学的な知見が、マスコミを含めてこれだけ喧伝されるようになったのは、なんといっても機能的磁気共鳴画像法(fMRI: functional magnetic resonance imaging)が20世紀の終わりに確立され、様々な日常的なトピックに関する成人の脳活動が非侵襲的に計測できるようになったことが主たる理由だろう。「好きな人の顔画像」に特定の脳領域が反応する。他人をうらやむ気持ちと相関して反応する場所がある。こうしたわかりやすいテーマだけでなく、自閉症やADHD特有の脳活動というものも次々と報告されている。日常生活における心の働きの背後に脳がしっかりと活動していることがわかり、脳科学は人文社会学的な活動にも入り込むようになった。神経美学、神経政治学、神経経済学、などのキーワードなどはその典型である。近年の発達障害研究のブームも、そのベースには、fMRIによる研究があってのことだと考えられる。
もちろん、こうしたブームには一定の留保もつく。脳活動を捉えることさえできれば、人間の心の謎を科学的解明できるとする単純な理系の発想に出会うこともあるが、実のところそのような考えは誤りである。詳しくは拙著『ゼロからはじめる心理学・入門』の序章をご覧いただきたいが、簡単にいえば、脳をいくら調べてみても、そこにあるのは単なる電気信号の配列だけであり、心理学が対象とする知覚、認知、感情の実体は見つからないからである(金沢、市川、作田、2015)。
例えば錯視、すなわち「ある図形において、定規で計った長さより線分が長く見える」という知覚状態を考えてみる。(実験実習1を履修した学科の皆さんなら、ミューラー=リヤー錯視の測定の回を思い出していただきたい)。確かに脳を計測してみれば、その「長く見える」という報告に「相関する」脳活動は存在するかもしれない。しかし「本当に長く見えているのか」は、脳活動からわかるのではなく「長く見える」という被験者の言葉での報告から、間接的に推測しているにすぎないのである。
とはいえ、「脳が活動している」という事実は、一般の人にはわかりやすい。これは共同研究を行っている医師の方から聞いたのだが、患者さんに説明する際には、心理学実験の行動データよりも、脳活動の図を示した方が納得いただきやすい、とのことであった。例えばご自分の家族が発達障害である、との診断を受け入れる際にも、実際に「右前頭葉の活動が定型児とは異なる」といったデータを見せられた方が、腑に落ちることがあるらしい。「脳活動を計測する」ということは、最大のデモであり現場では威力抜群というわけだ。
しかも「脳が活動している」という事実は、専門家にとっても、研究を進めるための重要なヒントをもたらす。例えば近年のAI研究が、脳活動計測がもたらす数々のインパクトに背中を押されていることは否定できないだろう。「機械が意識をもつのか」といった問いは古くて新しい問であるが、AIが自然にしゃべり始め社会に入り込んでくるにつれて、その問いかけはますます重要になっている。目の前にある物体としての脳が、ニューロンの電気信号の回路から成り立つことが実際に活動として捉えられた時、同時に「意識がある」と被験者が主張する心の状態が「相関」としても捉えられる。こうして、否定派も肯定派も巻き込みながら、AIやロボットが意識を持つ条件についての熱い議論が、世界最先端の研究として今まさに交わされているのである。このあたりの学術的な流れについては、例えばモナッシュ大学の土谷尚嗣先生が主催する「クオリア構造学」のHPを参照いただきたい。筆者もこのプロジェクトに公募班員として参加させていただいている。
心理学を学ぶ学生の皆さんは、常に議論を巻き起こしながらも、今まさに展開しつつある脳計測の科学的インパクトを感じていただければ、と思う。そして、脳活動を通じて、心ことは何か、それは科学的にどう捉えられるのか、という心理学の究極の問について考えていただければ幸いである。
Kanazawa, S. and Dan, I. (2018). Editorial: fNIRS in Psychological Research: Functional Neuroimaging Beyond Conventional Fields, Japanese Psychological Research, 60(4), p.191-195.
金沢創、市川寛子、作田由衣子 (2015). ゼロからはじめる心理学・入門 有斐閣