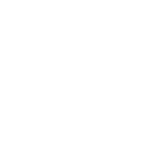金沢ゼミ・中級演習(3年次)の風景

授業では、各人が英語で論文をもちより、論文を紹介しながら、発達障害とは何か、社会性の基盤となる行動はどのようなものがあるか、脳活動はどうやって計測するのか、顔がわかるとはどういうことか、匂いを嗅いでいる時はどのような脳活動がみられるか、音楽療法は発達障害支援に有効か、といった多様なテーマについて皆で学んでいます。英語を読む力も自然とつきまして(ただし心理学の論文だけですが!)、皆さんも気が付かない間に総合力がぐんぐんアップしていることがわかります。
ゼミではまず、英語論文とはネット上のどこにどのような形で落ちていて、どうやって探し出すのか、自分の興味をどうやって専門的な論文を探すことにつなげていくのか、といった主に論文の探し方を学びます。教科書で習う知識の最前線が、いつでもネットで見れるという体験はとても楽しいものですね。
これば毎年のことなんですが、当初は英語なんて見るのもイヤだった皆さんも、アブストラクト(論文の要約です)を丁寧に読み解いていくことで、科学的な論文で出てくる典型的な表現を学んでいきます。そこから心理学の専門用語を英語で学ぶことで、実は英語論文とはいっても、決まったパターンで読めることがわかってくるのです。
論文で出てくる図表の見方、実験の方法のセクションで用いられている用語などは、1年生や2年生で行ってきた実験実習の授業が役に立ちます。すっかり忘れていた(笑)統計用語なんかも久しぶりに思い出すことで、一度聞いたことがある用語や考え方が、実際に研究の現場で使われていることを実感し身についていくことになります。
また、授業では、現場で活躍している心理士の方を呼んで発達障害支援のリアルなお話を聞く機会も設けています。発達障害支援の現場でどのようなことが課題になっているのか、といったお仕事の話だけなく、支援者のワークライフバランスのお話しなど、どんな生活スタイルで仕事に臨んでいるのかまで含めた興味深いお話しを聞く試みです。学生さんも活発に発言して大いに盛り上がりました。
関連記事