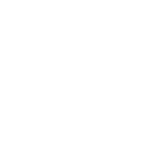社会心理学の授業風景:“三人寄れば文殊の知恵”?

社会心理学の授業では、人々が集まることで起きるさまざまな集団現象について学びます。例えば、他者から影響を受けて人々が行動を変化させる過程(社会的影響過程)や、対人関係を資源の交換と捉えて定式化する理論(社会的交換理論)、あるいは集団での問題解決・意志決定を行うことの合理性などです。
特にこうした集団現象を、自らの生存確率を高めようとする合理的な個体の判断が集積した結果として捉えることで、時にとして(社会)心理学者が陥りがちな「曖昧な概念を用いたなんとなくの記述」に陥ることなく、科学的な説明をつけることを目的としています。
例えばある回では、人々が集まって問題に取り組めば、個人では思いつかなかったような新しいアイディアが生まれて、たとえ難しい問題でも解けるようになるという信念(“三人寄れば文殊の知恵”という信念)について検討しました。つまり、集団での問題解決は、本当に個人で取り組むよりも効率的なのでしょうか?

この点についてLorge & Solomon(1955)では、実際に集団で問題解決した際の正答率と、「集団成員が別々に問題に挑戦し、その中の1人でも正答できたら集団は正答できたことにするという機械的集約モデル(基準モデルと呼ばれます)」に基づいた正答率の予測値との比較をしています。
その結果、集団の正答率は機械的集約モデルに比べて高い正答率を持つとは判断できない、つまり集団での問題解決はいつでも人々が期待するほど高い効率性を持つわけではないが示されています。
理由は、その後の研究(例えばStasson et al., 1991)によれば、集団での問題解決場面では、問題に取り組む人々の持つアイディアや意見を集約・共有し、それらを発展させることが難しいためだと考えられています。つまり、集団過体において個々人の持つポテンシャルが発揮されず、失われてしまうというわけです。個々人の可能性を引き出すファシリテータの存在が重要だというわけです。
こうした研究は、私たちの社会的な常識(例えば“三人寄れば文殊の知恵”という信念)を科学的な視点から検討し、そうした常識がどのような条件では成立するのかなど、さらに理解を深めるのに役立ちます。

〈引用文献〉
・ Lorge, I., & Solomon, H. (1955). Two models of group behavior in the solution of eureka-type problems. Psychometrika, 20(2), 139–148. https://doi.org/10.1007/bf02288986
・ Stasson, M. F., Kameda, T., Parks, C. D., Zimmerman, S. K., & Davis, J. H. (1991). Effects of assigned group consensus requirement on group problem solving and group members’ learning. Social Psychology Quarterly, 54(1), 25. https://doi.org/10.2307/2786786