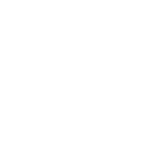仮想現実空間での実験(竹内ゼミ)

竹内ゼミ(中級演習・特別演習)のメインテーマは「色彩心理学」ですが、人工知能や仮想現実(VR)空間といった、今はやりの技術を学ぶことができます。私はVR空間内で視覚探索実験を行い、それを卒論として完成させました。VR空間内の実験では、ヘッドマウントディスプレイ(HMD)を頭部に装着して視覚刺激を観察し、手に反応用のコントローラを持ちます。HMDはコンピュータとコードでつながっているのですが、かなり長いので、ある程度自由に動くことができます。図の実験では、実験参加者がVR空間内のいろいろな箇所を探索しています。
VR空間内の風景や事物は、Unityというソフトウェアで作ります。家や道路、車などの部品を並べて自分だけの街を作り、その中を歩いて探索することができます。それだけではなく、空間内のあらゆる場所に行くことが可能です。私は、図にある高いビルの屋上の端っこに立って下を見てみたのです。すると、すこし足が震えてしまいました。これは現実ではないと頭ではわかっていても、身体反応が起きてしまうくらいの没入感があり、とても不思議です。
実験では、反応時間を取ったりそのデータを記録したりといろいろな操作が必要です。そうした操作はプログラミング言語を使って書く必要があります。私はプログラミング未経験だったのですが、竹内ゼミの先輩方がこれまでに作成したプログラムを切り貼りして、自分の実験プログラムを作ることができました。
VRはゲームだけでなく、教育やセラピーなど、さまざまな分野で利用されています。卒論を通してVRに詳しくなれてよかったと思っています。