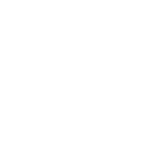2023年度 心理学科卒業 百貨店外商事業部相原花凜 さん

心理学に興味を持ったきっかけはなんですか?
人の行動や気持ちの変化に興味があったことがきっかけです。昔から「どうしてこういう行動をするのだろう」「なぜこの選択をしたのだろう」と、人の考え方の背景にあるものを知りたいと思うことが多く、自然と心理学に惹かれていました。特に、人が無意識にとる行動や、環境によって変化する考え方の違いに面白さを感じ、学んでみたいと思うようになりました。
お仕事の内容、やりがいを教えてください!
百貨店の法人外商部で商品企画担当として働いています。法人のお客様に向けて、ギフトや記念品、オリジナル商品などを企画し、提案からサンプル作成、製造の進行管理、納品まで一連の流れに関わる仕事です。この仕事の一番のやりがいは、自分のアイデアが実際の「モノ」として形になる瞬間に立ち会えることです。企画というのは、同じ依頼内容でも担当する人によって全く違う方向性のものが生まれます。自分の視点や発想がちゃんと価値としてお客様に届いたという手応えが、働く上で大きな自信にもつながっています。また、法人外商の仕事は、百貨店という館の枠にとどまらず、企業や団体など、より幅広いお客様へ企画を届けられる点も魅力です。お客様ごとに求めているものが違うため、ひとつひとつの案件がオーダーメイドです。その難しさと面白さの両方が、自分を成長させてくれていると感じています。百貨店がもともと好きで、「幸せを感じられる場所」と思ってきたからこそ、百貨店を通して、自分の企画したものが誰かの喜びにつながるこの仕事に、大きなやりがいを感じています。
現在のご職業に就職された理由はなんですか?
百貨店が昔から好きで、「ほしいものをやっと見に来られた瞬間」「大切な人への贈り物を選ぶワクワク」「久しぶりのお出かけを楽しむ気持ち」など、そういった“小さな幸せの集まる場所”に惹かれてきました。就職活動では 百貨店で催事など企画の仕事がしたい と考えていました。研修中に、百貨店の外でも幅広い人々へ企画を届けられる「法人外商の商品企画」という職種があると知りました。より広いお客様に、自分の企画で喜んでもらいたい という想いから、法人外商の商品企画を希望し、現在の職に就きました。
在学中、好きだった授業はなんですか?
心理学の授業はどれも興味深く、全体的にとても好きでしたが、特に思い出深いのは3〜4年生で所属していた伊村ゼミです。班ごとに進めた研究や卒業論文では、「人間が無意識のうちにどのように区別しているのか」といった、自分が特に興味を持っていたテーマを深く掘り下げることができました。実験を組み立ててデータを分析していく過程は大変ではありましたが、その分だけ自分の考えが整理され、理解がどんどん深まっていくのがとても面白かったです。発表では、自分の言葉で研究内容を伝える難しさと向き合いながらも、学びが形になっていく実感を得られた、大切な授業だったと感じています。
在学中、特に力を入れたことはなんですか?
在学中に特に力を入れたのは、ゼミ活動とアルバイトです。アルバイトは「多くの人と関わりたい」という思いから、ケーキ屋さん、もんじゃ店、タピオカ店、百貨店での帽子販売、コールセンター、高級レストランなど、さまざまな環境で接客を経験しました。年齢層や国籍、求められる接客レベルの違うお客様と関わる中で、相手がどんな対応を求めているのかを瞬時に判断する力が身につき、期待以上のサービスを提供できるようになりました。ゼミ活動では、発表準備を通してまとめる力・伝える力を鍛え、質疑応答ではその場で考えて対応する瞬発力を培うことができました。これらの経験は、現在の仕事でも相手に合わせた提案やコミュニケーションに活きています。
心理学科の後輩へメッセージをお願いします!
心理学科での学びは、どの仕事に就いても自分の知識として生かしていけるものだと思います。心理学に興味を持ったみなさんはきっと、「もっと知りたい」「人の考えや行動って面白い」と感じる瞬間が多いのではないでしょうか。様々な視点から物事を見る姿勢や、他の人の考えを理解しようとする姿勢は、社会に出たときに大きな強みになります。実際に働くようになると、相手の気持ちや立場を想像したり、状況を冷静に読み取ったりする場面がたくさんあり、心理学科で学んだことが自然と役に立つことを実感します。そして何より大切にしてほしいのは、“自分の好き”や“興味が動く瞬間”です。授業、ゼミ、課外活動、友人との出会いなど、大学生活には心が動くきっかけがたくさんあります。その感覚を大事にすることで、自分がどんなことにワクワクするのか、どんなことをやってみたいのかが見えてくると思います。まずは、自分の興味や好きな気持ちを大切にして、やりたいことを思う存分できる大学生活をぜひ楽しんでください!
November, 2025
※内容はインタビュー当時のものです